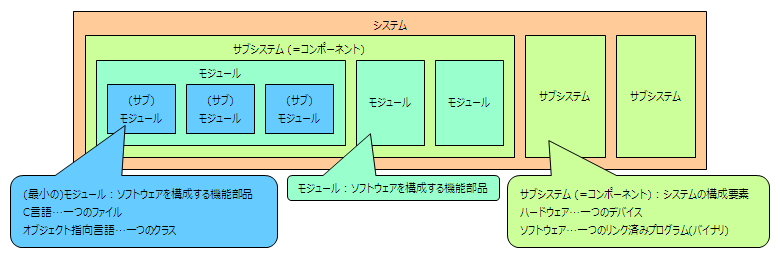
| 区分 | 説明 | モジュール強度 | |
| 暗合的強度 | 無関係の機能を一つのモジュールにまとめる | 弱 | |
| 論理的強度 | 論理(≠機能)的に関連のある機能を一つのモジュールにまとめ、 どの機能を使用するかを引数により決定する |
||
| 時間的強度 | 実行時のある時点で利用される複数の機能を一つのモジュールにまとめる (機能間の関連は不問) |
||
| 手順的強度 | 必ず順番に実行される複数の機能を一つのモジュールにまとめる | ||
| 連絡的強度 | 手順的強度 + モジュール内の機能間でデータの受け渡し | ||
| 情報的強度 | 特定の同じデータを扱うための機能を一つのモジュールにまとめる | 構造化設計の目標 | |
| 機能的強度 | モジュールが単一の機能のみを提供 | 強 | |
| 区分 | 説明 | モジュール結合度 | |
| 内部結合 | あるモジュールが別のモジュールの内容・命令を直接参照・使用する | 強 | |
| 共通結合 | 構造を持つ大域データを複数のモジュールで共用する | ||
| 外部結合 | 構造を持たない大域データを複数のモジュールで共用する | ||
| 制御結合 | 相手のモジュールの機能に影響を与える制御情報 (機能コード、スイッチなど)を受け渡す |
||
| スタンプ結合 | モジュール間で、構造を持つ引数(構造体など)を受け渡す (不要なデータを全く含まない場合は「データ結合」に分類される) |
||
| データ結合 | モジュール間で、構造を持たない引数を受け渡す | 弱 | 構造化設計の目標 |